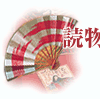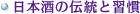

四季の変化のはっきりしたこの国では、豊かな自然の風物に恵まれ、そこから自然を愛でながらお酒を楽しむという、贅沢な日本人ならではの文化をはぐくんできました。
|
 |
春といえばかかせないのが「花見酒」。桜の花見は奈良、平安の頃から行われていました。
有名なものに、太閤秀吉の豪華絢爛な「醍醐の花見」がありました。娯楽の少なかった江戸の頃は、花見は庶民の最大のレクリエーションでした。 |
 |
「夏越しの酒」は六月の晦日に半年の汚れを流す意味から飲むお酒です。この時期は田植えも終わり、ほっと一息入れる時期。これからの暑い夏を乗り越えるために祈りながら飲む、暑気払いのお酒でした。 |
 |
中秋の名月といえば旧暦の八月一五日。満月の光を浴びながら酒を飲み交わす「月見酒」。江戸の頃は、川舟を繰り出してにぎわい、隅田川界隈の料理茶屋は大繁盛し、ひと晩のお酒の量は大変な数になったといわれます。
月を見ながら、季節の変わり目をしみじみと味わうお酒です。 |
 |
しんしんと降り続く雪を見ながら「雪見酒」を楽しむ。何とも風流なこの習慣は、平安の頃、あの紫式部も行っていたといわれます。当時は雪の中を、わざわざ牛車を仕立てて野山に出かけたり、江戸の頃は船を出して雪を楽しんだといいます。
|
|